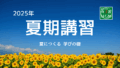寺子屋はじめの2025年度入試は、3月11日で全員の全日程が終了した。
今年度は中学受験生がおらず、大学受験と高校受験での勝負。少人数制の塾なので受験生の総数は少ないものの、チャレンジ精神旺盛な生徒が揃っていたこともあって、非常に際どい勝負の連続だった。12月からずっと気が休まる日はなかったと言ってよい。
大学受験
3年連続MARCH輩出に加え、早稲田大学の合格者も出た。早稲田の一般入試はギリギリ勝負の連続でなかなか思い通りにもいかなかったが、なんとか無事に合格をいただけて安堵した。
東京近郊、という地域では、「国公立より私立」という傾向が顕著だ。むろん東京一科(東京・京都・一橋・東京科学)は別だが、文系では特に、地方旧帝大より早慶、というのは珍しくない。むしろ普通では?というくらい。
理系でも、「地方の国公立よりも家から通える理科大(東京理科大)」という傾向は最近大きくなってきている印象がある。
なにより、偏差値や学部学科の傾向など全部抜きに、また時代の流れも変わってきている中、今なお「MARCH」優位というのは変わらない。
そうした中で、MARCHや早慶を目指す生徒が一定の結果を出す助力ができたのは喜ばしいことだ。
女子大を積極的に受験する生徒が非常に多いのも特徴だった。女子は全員、いずれかの女子大を受験し、進学する者もいる。私が「選択肢には入れるといい」とは助言しているものの、それぞれに良さを感じ、きちんと自分の受験戦略、また将来設計に組み込んでいるというのはひとつ特筆すべきところだと思う(女子大の経営が~とか偏差値が~というのは別の話)。
首都圏の私立大学志望者は、おおむね4~8校くらいを、受験スケジュールをうまく組みながら受験することが多い。助言はするが、最終的にどこをどう受けるかは受験生自身が決めて、スケジュールも組む。そういうことがきちんとできるというのも、大学に進学する上では必要なことだと考えている。自分の人生であって、人任せにするものではないし、金銭的な負担についてはしっかり親と相談して納得を得るのもまた必要なステップと考えている。
私は、私立大学の共通テスト利用入試は「当てにならない」を信条としていて、実際に当てにはならないのだが、ここ数年はかなり計算して戦略に組み込んでいる。
実際、今年も、100%とはいかないまでも、かなり理想に近い形で共通テストを使うことができた。
特に文系では、国語や英語は「根本的な力」が鍛えられれば、あとは形合わせだけで必要なスコアを狙いやすい。偏差値50を切る公立高校の生徒でも、努力の量と方向性、戦略・戦術を誤らなければ、国語で8割以上の換算になって、悠々とひとつ合格をいただけることはあるのだ。
大学受験、特に一般入試は性質上、「第一志望」はどうしても挑戦圏のレベルになりがちである。現実的に届く可能性があるが、本番でなにか一つでも要素が欠けると合格は難しい、というレベル。故に、なかなか辛い入試が続いた生徒もいるのが現実。私が「高1からでは間に合わない」とよく言うのはこういう世界だ。理想と現実のバランスをいかに取るか。生徒たちがこの大学受験という経験を通してそれを学び、今後の長い人生に活かしてくれることを願ってやまない。
高校受験
各自の学力もバラバラで、受験の方針も様々。全員、自分の将来設計に見合った選択という意味では間違っていなかったと思うし、結果にかかわらず、それぞれに頑張りは評価できるものだと思う。
正直、誰一人として「安全な勝負」をした生徒はいないと言ってよい。自分の希望を第一に果敢に高倍率勝負をした生徒もいるし、千葉県の公立高校は定員割れをしていても不合格になることはあるから(実際、近隣でもあった)、特に得点力に不安のある生徒は必ずしも「勝てる勝負」ではなかった。
そういう中で、各自の中では様々な思いが去来していることと思うが、無事に受験を終えられたことは良かった。みんなおつかれさま。
正直、受験勉強については、「もうひとつのなにか」がそれぞれに欲しかった。それは敢えて具体的に言語化するのであれば、小テストに真剣に取り組むであるとか、丸付けの仕方をいいかげんに直すとか、そういうものだ。どれだけ指摘されても直せなかったところ、抜いてはいけないところで手を抜いてしまったところ、各自がそのような「自分の弱さ」にどれだけ向き合えたか。
本命に不合格になった生徒は、自省の機会を得た。それぞれに自分の半生を振り返って、今後どうしたらいいのかを考えたろう。合格してなおその機会を持てる中学生は本当に少ないはず。ぜひともみな自省して、あらためて新しいステップに向かう気持ちを作ってもらいたい。
と、私自身本気でそう考えているのだが、やはり塾での指導および受験の結果については、個人としては重みを感じるし、責任を感じるところがある。これは受験の結果についてだけではない。むしろ合格して希望通りに進学できる生徒に対してもかなり重く考えなければいけないものがある。
まだあどけなさが残る若者が、自らに足りない「なにか」を明確に自覚し、どう努力してそれを克服するかというのを自身でやっていくのはとても難しい(できる子ならばそもそも勉強では困らない)。それを助けるのが当塾の仕事だ。その仕事を十全にできたのかと自省するとやはり欠けるものはあったと思うし、反省は尽きない。そもそも、成長過程にある生徒たちをサポートするにおいて、十全な仕事などあり得るのかというと、それはない気がする。やってもやっても足りない、常に反省材料が湧いて出てくる。教育というのは因果な仕事だなぁ。
前に進もう
受験を終えた諸君、前に進もう。
あえて言うが、結果はもういい。進路は決まったのだから、反省すべきことは反省して、4月からの新生活、期待に胸を膨らませて進もうではないか。
大学生になるということは、学問の入口に立つということだ。本を読んだり英語に磨きをかけたり、自らの知を磨くことに尽力してほしい。また、世界が広がって新たな遊びを覚えることになる。魑魅魍魎、奸佞邪知の輩もそれに伴って近づいてくるだろう。十分に気をつけたし。
新高1の諸君は高校生を謳歌してほしい。そしてそれは勉強と両立できる、というよりも、勉強することそのものが謳歌することの一部分と意識して、今この入学前の3月からしっかり勉強するとよい。県下トップ校の上位層以外は、「もう大学受験には間に合っていない」ことを前提に考えよう。
そして、難関大を目指すということは、お勉強だけしていても駄目である。幅広く高校生活を充実させて血肉を強くしよう。ダラダラとリールやショート動画を追うようなつまらない時間の使い方はするな。120%打ち込めるものに時間を使おう。部活に打ち込むならそれはそれでいい。勉強しない言い訳にはするな。
新年度の受験生へ
新小6、新中3、新高3のみなさん。
ようこそ、受験の世界へ。
「やる気が出ない」という言い訳は不要です。そんなものに依存せず、やるべきことを毎日やること。どれだけ努力しても女神が微笑むかは分かりませんが、努力をしない者には決して微笑むことはない。
受験はみなさんが成長するための大きな壁です。
親も私も、手伝えることは「壁をぶち破るための力をつけること」だけ。ぶち破るのに使えるのは自分自身の力のみ。
勉強しろと言われているようでは駄目。勉強するのを親が止める、私が止めるくらいやりましょう。それくらいになれば、自ずと道は拓けてきます。
そして新高1、高2のみなさん。
今の大学受験一般入試、3年間で間に合うようにはできていない。推薦?総合型?それこそ高1の最初からコツコツ頑張らないと受験資格すら得られないじゃありませんか。不安を煽るわけではありませんが、君たちは最初から受験生なのです。これは紛れもない事実。
受験の方式は二の次なのです。いざ高3になったら、「取れるはずの指定校推薦を自ら蹴る」みたいなことは山程あります。行きたいなと思ったところに行きたいなら、実力をつけるのは必要不可欠。
自分の将来を切り拓くために、最初から、いや今すぐ、本気で頑張りましょう。